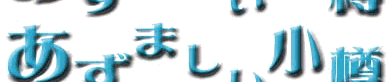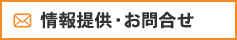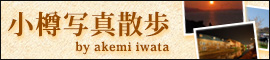特別展Ⅰ「能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界」が、4月26日(土)~6月29日(日)に市立小樽美術館(色内1・苫名眞館長)2階企画展示室で開催される。
千葉県四街道市にある松野藝文館(長谷川三香代表)所蔵の松野奏風と秀世父子の能画35点と、能画に合わせ外沢氏制作の能面26点を展示する。
 松野奏風は、1899(明治32)年東京に生れ、尾竹国観・月岡耕漁に師事。1938(昭和13)年「能姿五十彩」を出版。1940(昭和15)年刊行の観世流大成版謡本の編集に携わり挿絵を担当した。1963(昭和38)年に亡くなる。
松野奏風は、1899(明治32)年東京に生れ、尾竹国観・月岡耕漁に師事。1938(昭和13)年「能姿五十彩」を出版。1940(昭和15)年刊行の観世流大成版謡本の編集に携わり挿絵を担当した。1963(昭和38)年に亡くなる。
松野秀世は、1936(昭和11)年奏風の次男として東京に生れ、東京芸大日本画科卒。院展特待。能に親しむ会の招きで、2000(平成12)年に来樽し能舞台を見ている。2002(平成14)年に亡くなる。
松野父子は、能舞台で繰り広げられる能楽師の姿を絵画で表現する能画の名手として知られ、謡本の挿画も手掛け、各地の能舞台の松絵を描くだけではなく、先人の松絵を調査しその記録と解説を執筆している。同展展示の松野父子の能画は、北海道初公開となり、演目から描いた能画と能面をリンクさせて展覧できる貴重な機会となっている。
 開幕2日前の24日(木)には、奏風の孫の長谷川三香代表と、代表の母で奏風の長女・紗衣さんも会場で準備に携わっていた。
開幕2日前の24日(木)には、奏風の孫の長谷川三香代表と、代表の母で奏風の長女・紗衣さんも会場で準備に携わっていた。
生前の秀世は、代が変わることで奏風の作品が散逸することを恐れ、ひとまとまりにしたいと考えていた。その意思を継ぎ、2010(平成22)年に松野藝文館を建てた。6~9月は休館し、それ以外は金・土・日曜日に開館し、1月半で交換しながら展示している。
三香代表は、「今回は、能を観たことがない方や能の経験が少ない方にも楽しんでいただけるよう、比較的メジャーな曲を中心に、物語が知られている“道明寺”や“橋弁慶”、“八島”、“羽衣”などの能画を展示している。チラシにも掲載し、展示ケースの中の屏風で描かれた“松風”は、能の代表曲でとても人気がある。外沢先生の能面との関係では、能面がどんな風に使われているのか、能画を観ながら鑑賞してもらいたい。
 ひとつでもふたつでも絵を観ながら、物語を覚えて帰っていただけると嬉しい。テレビ放送でも良いので実際の舞台をご覧いただきたい。皆さんが能舞台に近づくきっかけになれば」と期待を寄せ、4月26日(土)に講演会を予定している。
ひとつでもふたつでも絵を観ながら、物語を覚えて帰っていただけると嬉しい。テレビ放送でも良いので実際の舞台をご覧いただきたい。皆さんが能舞台に近づくきっかけになれば」と期待を寄せ、4月26日(土)に講演会を予定している。
紗衣さんは、「秀世は、演目からさらにイメージを膨らませて描き、特徴的なのは面。写真はそのままだが、絵は描く人が自分の中で綺麗と思う形に描いている。動きによって悲しそうに見えたり嬉しそうに見えたり面の中に表れている。羽衣では、天に昇る姿が描かれほほえみを感じる。奏風にしても秀世にしても、能が好きで絵を描きながら、大勢の方に観ていただきたい、能を知ってもらいたい思いがあった」と話した。
 能面作家の外沢照章氏は、能仁会に入門し、面匠会で鎌田芳雲に師事。小樽に移住して22年。能面は130点制作、73種目を制作中。今年9月開催予定を数えると、小樽での個展は17回目。同館では、2年前に能面80点を展示する特別展を開催している。
能面作家の外沢照章氏は、能仁会に入門し、面匠会で鎌田芳雲に師事。小樽に移住して22年。能面は130点制作、73種目を制作中。今年9月開催予定を数えると、小樽での個展は17回目。同館では、2年前に能面80点を展示する特別展を開催している。
今回は、能画に合わせて能面26点を展示し、“隅田川”では、能面は目がくぼみ伏せがちで、頬にはえくぼ似の皺など年齢を積み重ねた中年の女性を表した能面“深井”を展示している。
外沢氏は、「今回の展示は、我々がまさに望んでいること。初めて能画と一緒に展示でき感激している。衣装などが揃って舞台ができる。能面だけではできない。能面は日本画の画材で描いているため、そういう意味では、日本画の能画はテキストになる」と話し、会期中の毎週土曜日13:30~16:30に在廊し、来館者の質問に応じる。
能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界
4月26日(土)~6月29日(日)9:30~17:00(入館16:30)
月曜日・4月30日・5月5日・7日・8日・9日・13日定休
市立小樽美術館(色内1)2階企画展示室 要観覧料
◎特別展Ⅰ 能舞台の華 能画~松野奏風・松野秀世と能面~外沢照章の世界(外部)
◎関連記事